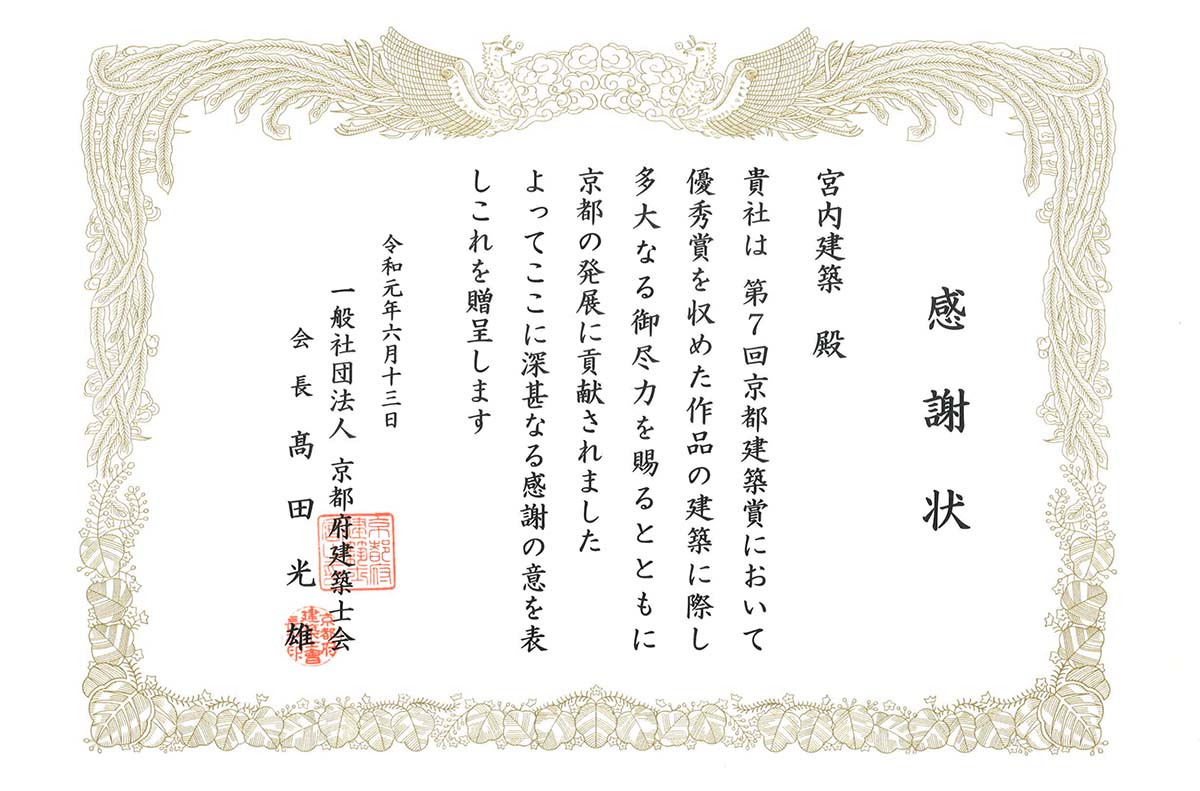建主さんのおじいさまの山の天川の材をふんだんに使ったスタイリッシュな家です。階段と玄関とリビングの境の障子の格子とを合わせたデザイン、トップライト、選り抜かれた照明やストーブなど、隅々まで建て主さんの鋭い感性が貫かれています。
正面真ん中に杉の引き戸のある玄関棟と母家とが合体した外観です。
玄関棟。美しい瓦屋根の軒を深く出しました。外回りはジョリパットでの左官仕上げで丸くしあげ、敷石には玄昌石を用いました。
杉の引き戸を雨や陽射しから守るために、軒をしっかりと出しています。持ち出している材も壁に合わせて丸く仕上げました。
広い玄関は外と同じ玄昌石を敷き、天井は杉の柾目の網代で仕上げました。
リビングから、玄関を振り返ると、奥の幅広の障子の格子と、手前の階段の段々がぴったりと合っています。腕のいい建具屋さんにそのように作ってもらいました。
リビングから2階にあがると夫婦寝室と子供部屋、1階奥には客間などに使う和室があります。
落ち着いた雰囲気の本格的な和室です。壁は二度塗り回した聚落仕上げ。床框やヤニ松、地板は桜、床柱は建主さんのおじいさまが孫のためにととっておいた天川産の銘木です。
襖の紙は江戸時代から伝わる板木で刷った唐長のもの。雲母が鈍く輝いています。引き手は漆塗りです。
和室の横の日当りのいいところにある台所の脇にはノルウェーのヨツール製のスリムなストーブがあります。
ヨツールのストーブは平面が正方形で、正面にも側面にも大きな窓がついています。火を焚くと、輻射熱で部屋全体があたたまります。
リビングに対面する台所正面。リビング側にはクルミ製の扉だけが見えていてスッキリしています。カウンタートップは黒い人工大理石。細長いですが、真後ろに天井までのなつくりつけ収納があり、使いやすい台所です。
リビングからガラス戸越しに外のデッキにつながっています。
杉板のデッキ。ここも軒をしっかりと、二重に張り出しています。
玄関方向に向かってデッキを見たところ。隣の家に接する縦張りの板壁に、通しのベンチをもうけました。人が集まって外でバーベキューをするときなどに使い手があります。
玄関側からデッキ奥を見たところ。細い横格子を入れ、デッキから外は見えても、外からはデッキの内側が見えないようにしてあります。
リビングの吹き抜けには、デンマークのルイス・ポールセンのライトを吊り下げました。吹き抜けの大空間を利用して、プロジェクターで大画面で映画を観ることもできます。
2階の廊下の手すりは細い無垢の材で仕上げました。すぐ上に天窓があり、トップライトを取り込んでいます。正面つきあたりは、夫婦寝室です。
寝室の手前に、玉杢の一枚板のテーブルをおきました。御主人のパソコンスペースとなります。
2階突き当たりの夫婦寝室。窓からバルコニーに出ることができます。
バルコニーから夫婦寝室を見たところ。
トイレの脇の手洗いスペースの正面の壁は、建て主さんの希望で真っ赤に仕上げました。ルイスバラガン風です。
1階のお風呂の手前の洗面台です。洗面台の前には大きな鏡を、上にはすっきりとした扉の収納棚をつけました。
浴室は、壁に青森ヒバを張った、ハーフユニットバスです。
ウッドデッキからの夜景。
デッキの夜景。ベンチを照らす照明をつけています。
玄関の夜景。引き戸の中心を、真上からぼんやり照らしています。